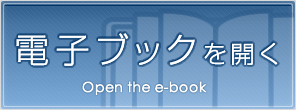戊辰戦争年表帖 page 10/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
軍を敗走させた。その時、頼母は容保に「今こそ和解の時です。敗けて降るは恥辱ですが、いったん勝って降るのは名誉の和解です。会津藩の面目を保つことですからぜひ帰順をされます様に」と進言したが、沸きかえる主....
軍を敗走させた。その時、頼母は容保に「今こそ和解の時です。敗けて降るは恥辱ですが、いったん勝って降るのは名誉の和解です。会津藩の面目を保つことですからぜひ帰順をされます様に」と進言したが、沸きかえる主戦派に一蹴されて容保の受け容れるところとはならず、彼は亡国の徒として誹そしられ登城を差し止められ甲賀町の屋敷に閉居することになった。 やがて西軍は十六橋から、戸ノ口原、滝沢峠を破り城下へ迫ってきた。 主戦派の家老田中土佐・神保内蔵助は西軍と激戦したが敗れ、二人共責任を負い、御典医の土屋一庵方で自刃した。 頼母はもうじつとしていられない。登城差止めの身も忘れて長男と登城した。彼を見送った妻千恵子34才は頼母との間に16才の長女を頭に「一男五女」が居たが、長男吉十郎11才を除いて五人の娘と共に自害した。次いで母律子58才その他西郷家に居た一族十四人も自決した。 丁度その時「土州軍」の「先鋒」中島信のぶ行ゆき(後の第一代衆議院議長)の一隊が進攻し邸内へ銃弾を打ち込んだがなんの反応もないので隊長中島が踏み込んで見ると邸内の各部屋は血しぶき、その中に二十一人が朱に染まって死んでいた。しかし、その血しぶきの中に一人の「乙女」が頭をもたげているのが目に映った。中島が近づくとその乙女はうつろな瞳で「そなたは敵か味方か」と聞く。中島がとっさに味方だと答えると、彼女は手にした懐剣を差し出した。介錯を頼むとの仕草である。中島は頭が下がる思いで戦場ではあるが南無阿弥陀仏と唱えながら太刀を振った。その乙女は頼母の長女細布たえ子こ16才であった。 この悲話は土佐の中島から沼津に明治初期暮らしていた西郷頼母に伝えられ、西郷の戊辰の記「栖せい雲うん記き」に残され、会津城下の悲劇として白虎隊と共に有名となっている。 現在、会津東山温泉の近くの会津武家屋敷として頼母邸が復元され、その中にこの状景が演出され、再現され、見学者の涙を誘っている。 この様に婦女子の悲劇が展開されている時、山本八重は弟の遺品を着て断髪をし、スペンサー銃を持ち、姉を亡くした中野優子らと勇猛果敢に西軍と対戦していた。 昭和3年建立された「なよたけの碑」が、善龍寺境内にある。碑名は自決した西郷頼母の妻千重子の辞世の歌「なよ竹の風にまかする身ながらもたわまぬ節はありとこそ聞け」からとったもので、碑陰には戊辰戦争で散った233名の会津藩の婦人名が刻まれている。右/なよたけの碑左/善龍寺26