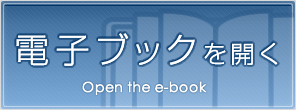戊辰戦争年表帖 page 16/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
50 慶応4明治11/27【1/3】「戊辰戦争-鳥羽・伏見の戦い」、はじまる。会津藩兵を先鋒とする旧幕府軍が伏見に集結し、幕府陸軍奉行・竹中重しげ固かた(1828~1891)を指揮官とし、諸藩兵や新選組など幕吏も吸収して....
50 慶応4明治11/27【1/3】「戊辰戦争-鳥羽・伏見の戦い」、はじまる。会津藩兵を先鋒とする旧幕府軍が伏見に集結し、幕府陸軍奉行・竹中重しげ固かた(1828~1891)を指揮官とし、諸藩兵や新選組など幕吏も吸収して、元伏見奉行所を本営とする。陸軍奉行並・大久保主膳正忠ただ恕くみが指揮の、鳥羽街道の別軍は、旧幕兵、桑名・大垣藩兵、佐々木只三郎の京都見廻組。幕府諸藩連合軍(15,000人)、鳥羽・伏見の両道から進軍。御香宮・城南宮を拠点とした薩長軍(5,000人)(長州軍参謀山田顕孝(顕義)・薩摩軍参謀西郷隆盛)と対峙。夕刻、幕府軍別働隊と薩長軍が、鳥羽街道では小枝橋付近で、伏見では元伏見奉行所と御ご香こうの宮みやを挟んで戦闘開始。00131/27【1/3】朝廷の命で、京の水戸藩本圀寺党約300名は、泉せん涌にゅう寺じ御陵を守る。00141/27【1/3】(京都)新選組隊士・小お幡ばた三郎(?~1868)、潜入中の薩摩藩邸を脱し、会津砲兵隊に合流する。00151/27【1/3】会津藩大砲奉行・林権助安定(1806~1868)、伏見豊後橋で負傷する。4日未明、淀城下へ退却。00161/27【1/3】会津藩大砲隊頭・白井五郎太夫(胤忠)(1832~1868)は、竹田街道から進むも土佐兵がおり、中立の土佐兵を避け、別路を進み、伏見堺町の薩摩藩邸に火を放ち、竹田街道を上るも、深夜には淀城下に退却する。00171/27【1/3】「墨染事件」で負傷した局長近藤勇いさみ(1834~1868)の代わりに、土ひじ方かた歳とし三ぞう(1835~1869)が率いた新選組、伏見の会津大砲隊を応援、さらに上鳥羽街道で激戦するも空しく、淀方面へ退却する。新選組隊士2名が戦死。00181/27【1/3】「鳥羽・伏見の戦い」がはじまり、八重兄・山本覚かく馬ま(1828~1892)は薩摩軍に捕えられ、相国寺門前の薩摩藩邸に幽閉される。覚馬は、蹴け上あげで薩摩兵に捕えられたとも、大坂にて捕縛されたともいう。覚馬は会津藩が大義を誤り賊名を得ることを憂いて会津兵を説諭しようとして伏見に駆けつけたが、道路はすべて塞がれていて通れなかった。やむなく山やま科しなより京に入って、会津藩の朝廷に敵する意のないことを申し開きしようとしたという。会津の山本家には、誤って、覚馬は四条河原町で処刑と伝えられる。00191/27【1/3】朝廷、「鳥羽伏見の戦い」で薩摩・長州・土佐に官軍の称を与える。さらに朝廷、大坂城攻撃を勅す。京の土佐藩兵らは、前藩主山内容堂(豊信)(1827~1872)の制止を振り切り、薩土密約に基づいて自発的に官軍側に就いて戦闘に参加という。0020小枝橋(古写真)西暦1868