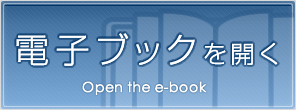戊辰戦争年表帖 page 18/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている18ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
52 慶応4明治11/27【1/3】下しも総うさ国のくに結ゆう城き藩10代藩主・水野勝知(1838~1919)、病気を理由に上京の猶予願いを新政府に提出する。当時、藩内は佐幕派と恭順派に分裂していた。結城藩庁は、現・茨城県....
52 慶応4明治11/27【1/3】下しも総うさ国のくに結ゆう城き藩10代藩主・水野勝知(1838~1919)、病気を理由に上京の猶予願いを新政府に提出する。当時、藩内は佐幕派と恭順派に分裂していた。結城藩庁は、現・茨城県結城市結城。00261/28【1/4】「兵庫沖・阿波沖の海戦(2日~4日)」。追いかける旧幕府海軍船「開陽」、阿波沖で薩摩藩軍艦「春日丸」と砲撃を交える。「平運丸」は瀬戸内海へ逃げたが、「翔凰丸」は、動けなくなり自焼。00271/28【1/4】徳川慶喜は、七、八分の勝利と聞いて、老中格大河内正まさ質ただ(上総国大多喜藩主)(1844~1901)・若年寄並・塚原昌義(1825~?)・幕府陸軍奉行・竹中重しげ固かた(1828~1891)の3名に、満足の意を表す沙汰書を出す。00281/28【1/4】(会津)会津藩家老・梶原平馬(1842?~1889)、藩士安部井政まさ治はる(1845~1869)と堀藤左衛門(外島機兵衛父)に書状を持たせ遣わし、上こう野ずけ国のくに前橋藩の意向を聞く。00291/28【1/4】「戊辰戦争-鳥羽・伏見の戦い-幕府軍、朝敵となる」。仁和寺宮嘉よし彰あきら親王(後の小松宮彰あき仁ひと親王)(1846~1903)、軍事総裁職から、宣下を受け徳川慶喜征討大将軍となる。その参謀は西郷吉之助(隆盛)(1828~1877)。仁和寺宮は、明治3年(1870)に宮号を「東伏見宮」に、明治15年(1882)に「小松宮」と改める。嘉彰親王が、節刀を賜り錦御旗を掲げ、正午に御所宜ぎ秋しゅう門もんを出て、14時に東寺に着陣。京中の男女とも競ひ出て拝観という。「官軍」となった薩長軍、士気大いに上がる。錦御旗は、薩摩藩の大久保利通や長州藩の広沢兵助(真まさ臣おみ)らの政治工作が功を奏したとも、岩倉具視の偽装ともいう。元御陵衛士ら、薩摩藩一番隊として戦う。鳥取藩兵が新政府軍の一員として前線に登場という。00301/28【1/4】会津藩大砲隊頭・白井五郎太夫(胤忠)(1832~1868)の軍、会津藩大砲奉行・林権助安定(1806~1868)、佐川軍、鳥羽・伏見両街道から怒涛の進軍で淀近くまで進出の新政府軍を迎撃、下鳥羽まで押し帰す。00311/28【1/4】会津藩の小姓頭浅羽忠之助(1831~1897)は、軍事奉行添役となり、松平容かた保もりの命を受け、鳥羽・伏見の戦場へ赴き、陣将・田中土佐(玄はる清きよ)(1820~1868)以下の諸将を慰労し戦況を視察した上で大坂城へ帰る。浅羽忠之助は、「鳥羽へ御使並大阪引揚の一件」を残す。0032梶原平馬仁和寺宮嘉彰親王錦の御旗西暦1868