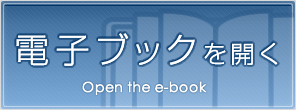戊辰戦争年表帖 page 22/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
56 慶応4明治11/30【1/6】征討大将軍に仁和寺宮嘉よし彰あきら親王が就任の情報らが、大坂城に伝わる。夜、徳川慶喜(1837~1913)が、名古屋藩(尾張藩)・福井藩(越前藩)に大坂城を任せ、松平容かた保もり(1836....
56 慶応4明治11/30【1/6】征討大将軍に仁和寺宮嘉よし彰あきら親王が就任の情報らが、大坂城に伝わる。夜、徳川慶喜(1837~1913)が、名古屋藩(尾張藩)・福井藩(越前藩)に大坂城を任せ、松平容かた保もり(1836~1893)・松平定さだ敬あき(1847~1908)・老中酒井忠ただ惇とう(1839~1907)・老中格松平(大河内)正まさ質ただ(1844~1901)・若年寄並兼外国総奉行平山敬よし忠ただ(1815~1890)・大目付戸川伊豆守安やす愛ちか(1834~1885)・外国奉行兼陸軍奉行山口直なお毅き(1830~1895)らを連れて、密かに大坂城を脱出、八軒家から舟で天保山沖に出、一旦、米国艦「イロクォイ号」に逃げ込む。00601/30【1/6】旧幕府軍艦「開陽」艦長・榎本武たけ揚あき(1836~1908)は、陸軍首脳部と連絡をとるため、午後、大坂に上陸。00611/30【1/6】摂津国尼崎藩、旧幕軍の脱走兵に備えて出張。尼崎藩(藩庁は、現・兵庫県尼崎市北城内)は、1月には新政府に恭順し、所領を安堵された。00621/30【1/6】(奈良)興福寺、旧幕府軍の伊賀越えを警戒し、伊賀越路・和わ束づか越路(現・京都府相楽郡和束)・多羅尾越路(現・滋賀県甲賀市信楽町多羅尾)・東海道筋を守備する。00631/30【1/6】紀州藩(紀伊国和歌山藩)、徳川宗家のため、一旦、佐幕派としての出兵を決める。00641/30【1/6】「赤報隊」。総督府の東征準備が整わないこの日、東征より先行して功を立てようと、前侍従綾小路俊実(のちの大原重実)(1833~1877)と典薬寮医生の山科元行(1828~1910)(のちの明治天皇侍医)、水口藩士油川錬三郎(信近)(1842~1908)ら30名ほどが、山花(現・京都市左京区修学院山ノ鼻町)の茶店「平八」に集まり、そこから、比叡山を越え、坂本(大津市)に出る。慶応3年12月12日、公卿の侍従鷲わしの尾お隆たか聚つむ(1843~1912)が勤王の兵を高こう野や山さんに挙げたことに、刺激されてなされたものであった。挙兵計画の中心にあった山科元行の背後には、議定岩倉具視(1825~1883)がいた。00651/31【1/7】播磨国小野藩(藩庁は、現・兵庫県小野市西本町)、大坂に藩兵が駐屯していたが、新政府に恭順。00661/31【1/7】朝、慶喜落去と聞いた、天満橋建国寺の武蔵国忍藩4代藩主・松平忠ただ誠ざね(1840~1869)は、紀州路からの退去を指示する。00671/31【1/7】公武合体を周旋していた、越後国長岡藩主・牧野忠ただ訓くに(1844~1875)、鳥羽・伏見の戦いの帰き趨すうを見て、大坂より江戸に向かう。長岡藩兵60名は、旧幕軍に属し、大坂城近くの玉津橋を守った。0068西暦1868松平容保松平定敬岩倉具視