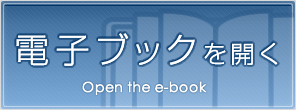戊辰戦争年表帖 page 24/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている24ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
58 慶応4明治11/31【1/7】新選組、大坂城二の丸に入るも火災により天満八軒家の船宿・京屋忠兵衛方に移る。00741/31【1/7】「鳥羽・伏見の戦い」。会津藩兵は朝までに大坂に戻ったが、大砲隊の白井隊と林隊の隊長は....
58 慶応4明治11/31【1/7】新選組、大坂城二の丸に入るも火災により天満八軒家の船宿・京屋忠兵衛方に移る。00741/31【1/7】「鳥羽・伏見の戦い」。会津藩兵は朝までに大坂に戻ったが、大砲隊の白井隊と林隊の隊長は負傷した。この日、天満八軒にて山川大蔵(のちの浩)(1845~1898)は、両隊兵を合して一隊となし、隊長を命ぜられる。上田伝治が組頭。山川は、最後まで大坂に残って会津藩の傷兵らを江戸へ護送することに尽力、帰藩し若年寄となる。00751/31【1/7】「戊辰戦争-鳥羽・伏見の戦い」。ほぼ終息するも、伏見・淀の大半が焼亡。00761/31【1/7】新政府、「徳川慶喜追討令」を発する。00771/31【1/7】豊後国森藩12代藩主・久留島通みち靖やす(1851~1879)、慶喜追討の請うけ書しょを提出。森藩庁は、現・大分県玖珠郡玖珠町。通靖は、前年11月24日国許を発し、同年12月13日入京していた。00781/31【1/7】因幡国鳥取東館新田藩10代藩主・池田徳のり澄ずみ(1854~1876)、慶喜追討の請書を提出。00791/31【1/7】河内国狭山藩12代藩主・北条氏うじ恭ゆき(1845~1919)、慶喜追討の請書を提出。狭山藩庁は、現・大阪府大阪狭山市狭山。00801/31【1/7】丹波国園部藩10代藩主・小こ出いで英ふさ尚なお(1849~1905)、慶喜追討の請書を提出。園部藩庁は、現・京都府南丹市園部町小桜町。00811/31【1/7】前年12月22日、上京し、新政府を支持する姿勢を示した、近江国西大路藩10代藩主・市橋長なが和かず(1821~1882)、慶喜追討の請書を提出。西大路藩庁は、現・滋賀県蒲生郡日野町。00821/31【1/7】近江国水口藩9代藩主・加藤明あき実ざね(1848~1906)、慶喜追討の請書を提出。水口藩庁は、現・滋賀県甲賀市水口町。00831/31【1/7】新政府、伏見で救米施行を行う。00841/31【1/7】(京都)新政府、仙台藩らに、倒幕の命を下す。が、経済的に到底戦争などできる状態ではない仙台藩の状況を鑑み、日和見の誹そしりに甘んじても、京にいた陸奥国仙台藩首席家老・但ただ木き土と佐さ成なり行ゆき(1817~1869)は動かなかった。00851/31【1/7】「赤報隊」。綾小路俊実(のちの大原重実)(1833~1877)、侍従・滋野井公きん寿ひさ(1843~1906)、相楽総三(1839~1868)、水口藩士油近錬三郎(信近)(1842~1908)、元御陵衛士の鈴木三樹三郎(伊東甲子太郎の実弟)(1837~1919)・阿部十郎(1837~1907)・篠原泰之進(1828~1911)・新井忠雄(1835~1891)らの諸グループが守山で合流。相楽総三は、京の薩摩藩邸で、西郷吉之助(隆盛)(1828~1877)に新たな任務、官軍の先鋒隊となることを命じられる。元御陵衛士、近江国水口藩士らも、薩摩藩や岩倉具視に指示されていた。00861/31【1/7】加賀国金沢藩13代藩主・前田慶よし寧やす(1830~1874)、上京を命じられる。00871/31【1/7】備中国岡田藩10代藩主・伊東長ながとし、京に向けて江戸を発つ。岡田藩庁は、現・岡山県倉敷市真備町岡田。00882/1【1/8】土佐藩参政・乾(板垣)退助(1837~1919)、1月6日編成の迅じん衝しょう隊たい大隊司令に任ぜられる。開戦したことを谷干たて城き(守部)(1837~1911)から報告を受けた土佐に在国中の板垣は、薩土密約に基づいて迅衝隊を編成という。0089西暦1868