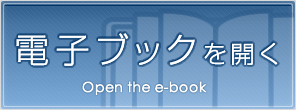戊辰戦争年表帖 page 6/26
このページは 戊辰戦争年表帖 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
1868慶応4(明治1)2/8【1/15】9代藩主酒井忠惇(老中)の播磨国姫路藩、備前国岡山藩に開城降伏。02342/8【1/15】北陸道鎮撫総督・高倉永祐、越後諸藩に勤王を誓わせる勅書を発令。02422/10【1/17】新政府、第一次....
1868慶応4(明治1)2/8【1/15】9代藩主酒井忠惇(老中)の播磨国姫路藩、備前国岡山藩に開城降伏。02342/8【1/15】北陸道鎮撫総督・高倉永祐、越後諸藩に勤王を誓わせる勅書を発令。02422/10【1/17】新政府、第一次の官制を発布。三職七科(1868.1.17設置~1868.2.3八局に改正)。総裁・議定・参与と、神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度の事務科である。02772/13【1/20】新政府軍(総督土佐藩家老深尾丹波・参謀乾(板垣)退助)、高松城を接収。03212/16【1/23】「桑名藩、恭順」。03682/16【1/23】徳川慶喜、新人事に改組。主戦論者を排除し、恭順論の主唱者勝義邦(海舟)を用いる。03702/16【1/23】出羽国庄内藩の江戸市中取り締まりが、廃止となる。03732/17【1/24】新政府議定・徳川慶勝(前尾張藩14代藩主)、三河・遠江・駿河・甲斐・美濃・上野の諸藩及び旗本の態度を勤王にすべく、尾張藩士40余名を派遣する。03812/18【1/25】英米仏蘭伊普6ヶ国が、日本内戦に対し局外中立を布告。03952/18【1/25】公卿参与・沢宣嘉、九州鎮撫総督に命じられる。03962/19【1/26】徳川慶喜、仏国公使ロッシュと会談し主戦論を拒否(27日も)。04132/20【1/27】この日夕刻、土佐藩兵、伊予国松山藩14代藩主・松平定昭の松山城を接収。04192/20【1/27】「赤報隊」。新政府、岩倉具視、年貢半減令を撤回。赤報隊は偽官軍とされていく。04212/20【1/27】松平氏を称する者、本氏に復す。04312/22【1/29】旧幕府、越後幕領のすべてを会津・米沢・桑名・高田4藩の預所とすることを命じる。04502/25【2/3】明治天皇、二条城太政官代に行幸し、倒幕の為の「徳川慶喜親征の詔」を発布。04762/26【2/4】(江戸)第9代松平容保、28万石会津藩主を降りる。許されて、家督を養子喜徳(水戸藩主・徳川斉昭の19男、徳川慶喜の異母弟)へ譲る。04932/26【2/4】「旧幕軍脱走」。旧幕府伝習隊の兵卒400名、脱走し、高田馬場に集まり八王子方面に向かう、後に大鳥圭介の軍に合流する。04962/28【2/6】「新政府、西国22藩に従軍令を発す」。05102/28【2/6】天皇親征の方針が決まると、征討軍が再編成され、それまでの東海道・東山道・北陸道鎮撫総督は先鋒総督兼鎮撫使に改称された。05112/29【2/7】「旧幕軍脱走」。夜、旧幕府陸軍の一部、脱走。2,000名という。第5、7、8、11、12歩兵連隊の兵士とされる。05363/1【2/8】(江戸)恭順の徳川慶喜、松平容保(会津藩9代藩主)・弟定敬(元桑名藩4代藩主)に、登城禁止を命ずる。0546西暦元号新暦【旧暦】出来事掲載頁4