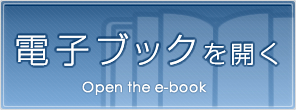院政・源平年表帖 page 17/20
このページは 院政・源平年表帖 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
西暦1156久寿3ほう(保元げん1)藤原頼長7月10日院政・源平年表「保元の乱」。夕刻、左大臣藤原頼長(1120~1156)、宇治より新院御所(白河北0447のりなが殿)に入る。また、崇徳上皇の側近である藤原教長(左京大....
西暦1156久寿3ほう(保元げん1)藤原頼長7月10日院政・源平年表「保元の乱」。夕刻、左大臣藤原頼長(1120~1156)、宇治より新院御所(白河北0447のりなが殿)に入る。また、崇徳上皇の側近である藤原教長(左京大夫)(1109~1180)や、散位平家弘(生年不詳~1156)・大炊助平康弘(家弘の弟)(生年未詳~1156)・右くろうど衛門尉平盛弘(家弘の弟)・兵衛尉平時弘(家弘の弟)・新院蔵人平長盛(生年不詳~1156)(平忠正の長男)・(崇徳院判官代)源為国(信西の娘婿)ら、各々祗候する。また、前大夫尉源為義(頼朝の祖父)(1096~1156)は、藤原頼長の強い要請により、離反した嫡子義朝を除く一族総出で、崇徳上皇方の麾下に入ためともる。衛門尉源頼賢(為義の四男)(生年未詳~1156)・八郎為朝(為義の八男)(1139~1170?)・九郎冠者(為義の九男源為仲)(1142?~1156)らである。前馬助平忠正(忠盛の弟)(生年不詳~1156)、散位源(多田)頼憲(生年不詳~1156)も各々軍兵を発し、集結する。崇徳上皇と頼長は、額を合わせ議定する。軍議で源為義・源為朝は、いったん退くこと、高松殿への夜襲などを献策したが、頼長はしんじつこれを斥けて、信実(生没年不詳)率いる興福寺の僧集団、吉野の軍兵など大和からの援軍を待つことに決したとされる。平忠正は、年来、左大臣藤原頼長に臣従していた関係から、崇徳上皇方に参じていた。7月10日「保元の乱」。第77代後白河天皇側の禁中守護に、源義康(1127~1157)が陣頭0448に伺候。この外、安芸守平清盛(忠盛の長男)(1118~1181)は、常陸守平頼盛のりもりなかつかさしょうすけ(忠盛の五男)、淡路守平教盛(忠盛の四男)、中務少輔平重盛(清盛の長男)らを率いて、さらに兵庫頭源頼政(1104~1180)、散位源(八島)重成(生年不詳~すえざね1159)、左衛門尉源季実(生年不詳~1160)、平信兼(生没年不詳)、右衛門尉平惟繁(生年不詳~1167)らも、勅定により参会、晩頭に及び軍兵は雲霞の如し。源よしとも義朝(1123~1160)は、崇徳上皇方の父・為義、弟の頼賢・為朝らと袂を分かち、東国武士団を率いて内裏高松殿に集結。平清盛は、崇徳上皇(第75代)(1119しげひと~1164)の第一皇子・重仁親王(1140~1162)と乳兄弟にあたるが、美福門院(藤原得子)(1117~1160)が「鳥羽法皇の御遺言だから、内裏へまいれ」と称され、参じるという。軍議で、信西(藤原通憲)(1106~1160)は、速攻を主張する義ただみち朝を支持、11日未明には、躊躇する藤原忠通(1097~1164)に決断を下させる。「高松殿址」碑が、中京区姉小路通釜座東入北側(高松神明社前)に立つ。高松殿跡碑(京都市中京区)53