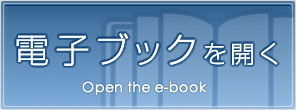明治・大正年表帖 page 14/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
118 明治106/30京都府派遣留学生8名の一人に選ばれた西陣の近藤徳太郎(1856~1920)は、3年半、パリの織物学院に学んで、明治15年5月に帰国し、京都府技師、京都織物会社、川嶋織物会社、フランス語教師(三高、同....
118 明治106/30京都府派遣留学生8名の一人に選ばれた西陣の近藤徳太郎(1856~1920)は、3年半、パリの織物学院に学んで、明治15年5月に帰国し、京都府技師、京都織物会社、川嶋織物会社、フランス語教師(三高、同志社)などを経て、明治28年(1895)4月、栃木県立工業学校の校長に招かれた。6/30京都府派遣留学生8名の一人に選ばれた稲畑勝太郎(1862~1949)、京都府の留学制度によりフランスに留学し、染色化学等を修める。明治18年(1885)帰国し、同19年には京都府染色講習所の教授になり、同21年には、京都織物株式会社の技師長に就任、だが、解雇され同23年に人造染料輸入の稲畑染料店(現・稲畑産業)を設立。軍服用カーキ色染めを創案で名を馳せる。後に、フランスのリュミエール兄弟が発明した撮影・スクリーン映写機「シネマトグラフ」を持ち帰る。―祇園祭は、明治6年から太陽暦上で、旧暦6月7日、14日に該当する日をもって巡行日とされてきたが、それでは祭日が一定せず不便であるため、この年、該当祭日(新暦7月17日、24日「後のまつり」)をもって恒久的に祭日と決定された。7/6 新島夫妻、和歌浦で休暇を過ごす。7/23 新島夫妻、京都に帰宅。7/―この月、京都府が麦酒造醸所を新高雄に開設。洛東清水の良水でビールを製造して、これを「扇印麦酒」と称して売り出す。清水寺本堂崖下の音羽川流域の渓谷・錦きん雲うん渓けいの紅葉の壮観さは、北山の高雄に比肩するとして「新高雄」と呼ばれた。―寺町通丸太町の自米屋・大沢善助(1854~1934)は、この年頃、同志社英学校初代校長の新島襄(1843~1890)から洗礼を受け、クリスチャンとなる。同志社英学校に米を卸したのが縁で新島襄と知り合い、親しくなった。大沢善助は、明治3年(1870)、会津中間部屋の元締め、大侠客・大沢清八(大垣屋清八)の養子となり、名を幸助と改名していた。善助は、やくざとなることを嫌って実業家を志していた。8/2 同志社分校女紅場を「同志社女学校」と改称する件、届出。8/20 新島夫妻、京都府葛野郡梅ヶ畑栂野寺(現在の京都市右京区)で、一週間ほど避暑。西暦1877稲畑勝太郎大沢善助桐野利秋(中村半次郎) ゴットフリート・ワグネル