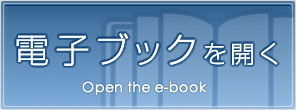明治・大正年表帖 page 18/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている18ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
122 明治115/24京都府上京第29区(御池東洞院上ル船屋町、元生糸改会所跡)に、古河太四郎(1845~1907)の尽力で、日本初の公立盲唖学校開校として仮盲唖院が開校式を行う。「日本最初盲唖院開学之地」石碑がある。....
122 明治115/24京都府上京第29区(御池東洞院上ル船屋町、元生糸改会所跡)に、古河太四郎(1845~1907)の尽力で、日本初の公立盲唖学校開校として仮盲唖院が開校式を行う。「日本最初盲唖院開学之地」石碑がある。5/―米国に留学しマサチューセッツ州スプリングフィールドに滞在中の岡部長なが織もと(1855~1925)、この月、新島襄に「岸和田の人々に基督教を伝道してほしい。そのために、岸和田の山岡尹ただ方かたという人に連絡してほしい」と依頼状を書く。岡部は、和泉岸和田藩の第13代(最後)の藩主であった。6/― この月、同志社女学校の生徒募集広告を出す。7/4同志社女学校を、J・D・デイヴィス宅(旧柳原前光邸)から上京第十一区今出川通常盤井殿町(現在の同志社女子大学今出川校地の一部)の新校舎に移転させる。同志社女学校新校舎は、デイヴィスらスポンサーと、米国のキリスト教婦人団体の募金で建設された。7/20新島襄(1843~1890)、岡部長なが織もと(1855~1925)の伝道依頼状で、岸和田に赴く。岡部に依頼された、山岡尹ただ方かた(1840~1915)邸も訪れる。尹方が社長であった、岸和田煉瓦株式会社の社章は十字架で、全ての製品に十字架の刻印が押され、同志社女学校静和館(大正1年竣工、現存していない)には、「岸煉」製の煉瓦が使用されていたという。山岡尹方らは、明治5年9月から、旧岸和田藩練兵場跡で煉瓦製造を始め、明治20年(1887)6月、第一煉瓦製造会社(後の岸和田煉瓦株式会社)を創立する。7/22地方自治の第一歩、三新法(郡区町村編成法、府県会規則、地方税規則)が公布される。地方の経費に関して府県会の決議を経なければ、知事・県令の職権のみではこれを徴収できないこととなり、この府県会の設置は、自由民権運動を刺激し、弾みをつける。7/22 京都府、全市を上京・下京に分ける。8/5 新島夫妻、人力車で比叡山へ行く。襄は1泊して翌日帰宅し、八重は12日まで滞在。8/―この月、山崎為ため徳のり(1857~1881)は、同志社より岸和田に派遣されキリスト教伝道を行う。同志社学生であった徳富猪一郎(蘇峰)(1863~1957)・健次郎(蘆花)(1868~1927)らも、修養会と伝道支援に岸和田に滞在。西暦1878古河太四郎山岡尹方上/同志社女学校最初の専用校舎(同志社大学提供)下/上京第十一区今出川通に移転後の校舎(同志社社史資料センター提供)