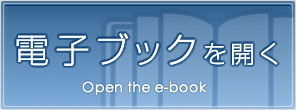明治・大正年表帖 page 4/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
108 明治8―この年、京都府知事の命で「京都産婆会」が組織され、産科医が市内各小学校で産婆講習会を開く。のち「京都産婆養成所」、「平安産婆学校」と名称変更。― この年、京都招魂社の神霊を、東京招魂社(後の....
108 明治8―この年、京都府知事の命で「京都産婆会」が組織され、産科医が市内各小学校で産婆講習会を開く。のち「京都産婆養成所」、「平安産婆学校」と名称変更。― この年、京都招魂社の神霊を、東京招魂社(後の靖国神社)に合祀する。霊山官祭招魂社(後の京都霊山護国神社)と霊明神社兼帯社の各藩の神霊とされる。―俵屋旅館(国登録有形文化財)(現・京都市中京区麩屋町通姉小路上ル白山町)は、石州(石見国)浜田の呉服問屋「俵屋」の京都店に、藩士が宿を求めるようになり、旅宿が本業になったとされている。現在残っているのは幕末元がん治じの大火後に再建されたもので、瓦には明治8年の銘が刻まれている。洗練された数奇屋風建築で、庭も全客室から見えるように配置が工夫されている。建物自体は、吉村順三(1908~1997)の設計で、本館増築は、昭和33年(1958)、新館は、昭和40年(1965)に竣工という。西暦1876明治9 1/1 新島襄(1843~1890)、ラーネッド、デイヴィスと3人で比叡山に登山。1/2山本八重、京都御苑内のデイヴィス邸において、J・D・デイヴィス(Jeromer.Deanr.Davis)(1838~1910)より洗礼を受ける。(京都における最初の洗礼式)。1/3八重(1845~1932)、新島襄(1843~1890)と、デイヴィス邸において、デイヴィスの司式により結婚。(京都における日本人の最初のキリスト教の式による結婚式)。八重はお手製のドレス姿。クリスチャン夫妻の誕生を祝うために列席したのは、同志社英学校の生徒たち、ラーネッド夫妻、八重や覚馬の友人など、40人ほど。質素な式で、当日の料理は、八重手作りのクッキーだったという。学生であった徳富猪一郎(蘇峰)(1863~1957)には、夫婦揃った目の前で、「頭と足は西洋、胴体は日本という鵺ぬえのような女性」とまで酷評する。―新島夫婦は、西洋的なクリスチャンホームを営む。八重は襄や宣教師婦人達から、洋食や洋菓子の作り方を教わり、襄のためにせっせと料理をした。派手な帽子・靴・和洋折衷の衣装で大いに人目を惹いた八重は、夫を「ジョー」と呼び捨てにしたり、レディファーストで夫より先に人力車に乗るのは当たり前。当時珍しかった自転車に乗ったり、仲良く2人並んで御所を散歩したり、人力車に夫婦相乗りして三嶋亭(中京区寺町通三条下ル桜之町)(明治6年創業)へ、すき焼きを食べに行ったりする。京すずめには「悪妻」「烈婦」として嫌悪の目で見られたが、彼女はどこ吹く風と、気にもとめなかったよう。八重にとっては古い日本の因習との戦いである。八重は英学校の聖書の授業に参加したこともあり、それに対して学生達は、襄に奥さんを連れてこないように申し入れたという。1/13「梅津製紙場」開業。洛西葛野郡梅津村(右京区梅津の松尾橋東)に、梅津製紙場(梅津パピール・ファブリック)が操業をはじめる。製紙場は、数ある府営の産業施設の中でも最大規模を誇った。本格的な和洋紙工場建設構想は、明治5年(1872)から検討され、これは府の顧問山本覚馬(1828~1892)と親しかったドイツ商人、ハルトマン・レーマンの献策であった。府は、ハルトマンの弟で、京都洋学校教師のルドルフ・レーマン(Rudolph.Lehmann)(1842~1914)を起用して設計、施工の一切を任せた。彼は、水利を考えて桂川東岸のこの地を選び、明治6年(1873)5月から建設を開始した。明治13年(1880)8月、磯野小右衛門に払い下げ。「日本最古の洋紙製紙場跡」碑が、右京区梅津大縄場町に立つ。西暦1875