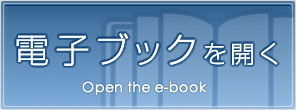明治・大正年表帖 page 6/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
110 明治92/―女紅場で働いた経験のある新島八重(1845~1932)、この月、J ・D ・デイヴィス(Jeromer.Deanr.Davis)(1838~1910)の妻の姉にあたるアメリカン・ボードのE・T・ドーン宣教師夫人と私塾を、新島宅で....
110 明治92/―女紅場で働いた経験のある新島八重(1845~1932)、この月、J ・D ・デイヴィス(Jeromer.Deanr.Davis)(1838~1910)の妻の姉にあたるアメリカン・ボードのE・T・ドーン宣教師夫人と私塾を、新島宅で始める。生徒はわずか3人ながら、八重はこれを「同志社女学校の基」と言う。生徒は3人で、その中の9歳の男の子はやめ、女生徒の姉の方は病気で亡くなり、妹もやめて、この私塾は、自然消滅となる。2/―内務省所管の博物館以外は地名などを加え○○博物館と称するようにという太政官からの通達により、この月、京都府営の博物館が「京都博物館」と改称する。明治16年(1883)、廃止。3/12 官庁を日曜日を定休日、土曜日を半休とする太政官通達が出される。4月1日施行。3/15 第五回京都博覧会開催「京都御所」(~6月22日)。105日間で241,764人が入場。3/28 政府、「廃刀令」を公布。陸軍卿山県有朋は「徴兵令が出た以上、帯刀は必要ない」と断行。武士の特権だった帯刀が全面的に禁止となる。3/― 月末、E・T・ドーン宣教師夫妻が、竹屋町に借家を構える。4/10A・J・スタークウェザー(Alice.Jennette.STARKWEATHER)宣教師、入洛。5月2日より女子のための私塾を宣教師館で、毎日授業を開始。のちの「同志社分校女紅場」である。4/10教部省、日蓮宗妙覚寺第35世日正・赤木日にっ正しょう(1829~1908)へ、不受不施派の「派名再興布教差許」の布達を出す。日蓮宗不受不施派の再興と布教が許可される。4/26襄の両親(民治、登美)、祖父弁治、姉(三女みよ)(1838~1879)、義甥・公きみ義よし(1860~1924)が、上州安中を引き払い、この日、新島襄の借家に移り住む。上京区新烏丸頭町(現・鴨沂高等学校の東南角)の借家離れであった。4/―3月にようやく教員許可が下りた、ドウェイト・ウィットニー・ラーネッド(Dwight.Whitney.Learned,)(1848~1943)、この月、同志社英学校着任。4/―この月、市郡小学校取締所(旧京都府中学、のちの京都第一中、京都府立洛北高等学校)を、「仮中学」と改称。5/13京都府権知事・槇村正直(1834~1896)ら、近代的な消防組織の基本を決めた「消防規則章程」を制定。町内の町火消は、府の指揮を直接受ける事になる。学区単位に編成され、その費用は区民が負担し、火災現場の指揮は警察の警部クラス、消防事務は区長と戸長が担った。西暦1876結婚して間もない頃の新島襄とその家族。左から八重、八重の母佐久、襄、父民治、母とみ、姉みよ(同志社大学提供)