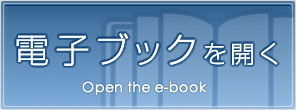明治・大正年表帖 page 7/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
111明治維新・大正ロマン 文明開化の京都年表帖5/22旧京都守護職邸跡地(現・京都府庁の辺)の独逸語学校を「医学予科校」として、「療病院」の所管に移す。5/―新島襄(1843~1890)、D・W・ラーネッド(同志社英学....
111明治維新・大正ロマン 文明開化の京都年表帖5/22旧京都守護職邸跡地(現・京都府庁の辺)の独逸語学校を「医学予科校」として、「療病院」の所管に移す。5/―新島襄(1843~1890)、D・W・ラーネッド(同志社英学校教員)(1848~1943)のため、京都府に「寄留届」を提出。5/―この月、京都の旧九条殿河原町邸に設立された英女学校を「京都府女学校及女紅場」と改称する。京都府立鴨沂高等学校の前身。5/―この月、半なから井い澄さやか(1847~1898)、京都療病院初代院長となる。編集掛には、神かん戸べ文ぶん哉さい(1848~1899)が命ぜられる。6/2 「京都府師範学校」(京都教育大学の起源)が開校される。京都御苑石薬師御門内、旧准后里御殿を仮校舎とする。6/12明治5年開通の新京極について、この日付の「郵便報知新聞」は次のように報じている。「下京第六区新京極通は、近時寺々の境内を開きし新町にて今は府下第一の繁盛を極め、昼夜諸人の輻ふく輳そうる場所なるが、北は三条通り南は四条に限り、わずかに四町ばかりの処に興行席を始めたる軒数のあらましは、芝居三座、浄瑠璃席三軒、軍書講釈、落語六軒、浄瑠璃身振狂言三軒、見世物十二軒、大弓九軒、半弓三軒、揚弓十五軒、料理屋十一軒、ちょんがれ祭文二軒、牛肉店二軒、煮売屋、ソバや、茶店の類廿九軒、この外饅頭、菓子、手遊人形、小間物、小鳥、読売歌、歯抜き、写真、袋物屋の類、筆紙に尽くしがたく、なかんずく古手物は殊にたくさんなり。」この後、「近来府下人の口癖にて誰も不景気を唱えざるなけれども、試みに文久以前に遡り見よ、かく繁盛のことありしや、まつたく地方官吏の特別なる尽力注意の致す所ならん。」と、新京極の繁栄をもたらした地方官吏すなわち槙村正直の功績を称えて結ばれている。7/25 温泉の男女混浴を許可。7/26 大阪・向日町間の官設鉄道汽車試運転を開始し、28日より仮営業する。8/12鴨川右岸の夷川下ルの「京都司薬場」は、同時期に設置された大阪司薬場に近かったため廃止される。8/21 「3府35県に統合」。豊岡県が廃止され、その一部、丹後国及び丹波天田郡が京都府に編入され、現在の京都府の区域が確立する。8/27「高橋お伝事件」。高橋お伝、吉蔵の喉を剃刀で掻き切る。29日、浅草の旅館で、首を裂かれた男の死体が発見された。明治政府は、道徳教育にお伝を利用する。すなわち、貞節の尊さを説くためにお伝(1850~1879)を稀代の毒婦に仕立て上げた。仮か名な垣がき魯ろ文ぶん(1829~1894)の「高橋阿伝夜叉譚」は、政府の要請を受けて執筆されたものだったのだ。西暦1876A.・J.・スタークウェザー(同志社社史資料センター提供)神戸文哉高橋お伝