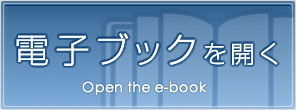明治・大正年表帖 page 8/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
112 明治98/29東京府新宿の土地開墾に困難を極める山科郷士に、千葉県千葉郡平山村・坂尾村・長峯村の入会地31町歩が払い下げられる。新宿大久保の土地を売却して、それを千葉県の開墾資金にあてて、この土地を「東....
112 明治98/29東京府新宿の土地開墾に困難を極める山科郷士に、千葉県千葉郡平山村・坂尾村・長峯村の入会地31町歩が払い下げられる。新宿大久保の土地を売却して、それを千葉県の開墾資金にあてて、この土地を「東山科村」と名付け、その開墾に集中した。「関東ローム層」という火山灰台地の原野であり、挫折を余儀なくされる。8/―旧京都市立有済小学校太鼓望楼(国登録有形文化財)(京都市東山区大和大路通三条下ル東側大黒町)(昭和27年移築)は、地域の火災等を半鐘で知らせる火の見櫓の機能と、太鼓を鳴らし地域への通信機能を果たすための施設で、この月に造られた。当初は木造2階建の下京第二十四番組北学校講堂の屋根に設けられていたが、講堂取り壊しの際、鉄筋コンクリート造の校舎屋上に移築された。木造2層で、屋根は宝形造。地域の行政施設としての役割を担っていた旧番組小学校の面影を伝え、現在も地域のシンボルとなっている。市内に残る唯一の太鼓望楼で、学校に併設されており火事と時刻を知らせていたものは全国的にも唯一現存するもの。9/5大宮通仮停車場(下京区梅小路頭町、現在の京都貨物駅付近)が設置される。官設鉄道の向日町・大宮仮停車場が仮開業して、大阪・京都間、仮営業開始9/7八重(1845~1932)、同志社の教員であり、医師・宣教師でもあったW・テイラー夫人の依頼で、嵯峨に同行。翌日、帰宅。9/9リロイ・ランシング・ジェーンズ(Leroy.Lansing.Janes)(1837~1909)の紹介で、8月廃校となった熊本洋学校の(元)学生ら海老名弾正(1856~1937)、金森通つう倫りん(1857~1945)、小こ崎ざき弘ひろ道みち(1856~1938)ら「熊本バンド」、同志社英学校に転入学する。伊勢(横井)時雄(1857~1927)は、翌年入学で、父は横井小楠、金森通倫・徳富蘇峰(1863~1957)・徳冨蘆花(1868~1927)は、母方の親戚にあたり、妻は山本覚馬の次女みね(峰)(1862~1887))で、父小楠横死後、伊勢姓を名乗った。9/11京都駆く黴ばい院いん仮院を、建仁寺内福聚院に設立する。京都府立洛東病院(廃止)の前身。現在の祇園甲部歌舞練場(東山区祇園町南側570-2)は、かつての建仁寺塔頭福聚院の跡。9/13 西本願寺末寺の内、真宗興正寺派が独立する。9/13 司法と行政が分離され、府県裁判所を地方裁判所と改称。有栖川宮邸の京都裁判所は、「地方裁判所」と改め、京都府と滋賀県を管轄させる。西暦1876旧京都市立有済小学校太鼓望楼(京都市東山区)W・テイラー夫人英学校最初の専用校舎(同志社大学提供)(同志社社史資料センター提供)伊勢(横井)時雄