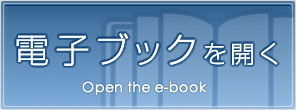明治・大正年表帖 page 9/22
このページは 明治・大正年表帖 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
113明治維新・大正ロマン 文明開化の京都年表帖9/18「同志社英学校最初の専用校舎、竣工」。相国寺門前(薩摩藩邸跡)に、同志社英学校最初の専用校舎二棟(第一寮、第二寮)、食堂・台所一棟が竣工、その捧堂式で、....
113明治維新・大正ロマン 文明開化の京都年表帖9/18「同志社英学校最初の専用校舎、竣工」。相国寺門前(薩摩藩邸跡)に、同志社英学校最初の専用校舎二棟(第一寮、第二寮)、食堂・台所一棟が竣工、その捧堂式で、新島襄(1843~1890)、山本覚馬(1828~1892)、D・W・ラーネッド(1848~1943)ら、演説する。実際、名実共に学校として開始したのは、この時、即ち初めて課程を定め、且つ自己の校舎に於て、生徒76名で授業を開始する。この頃、校舎に隣接する豆腐屋の廃屋を購入し、聖書を教えるための教室(いわゆる「三十番教室」)とする。現在のアーモスト舘管理人棟あたりという。現在は同志社キャンパスに組み込まれているが、当時は、キャンパスから道路一本を隔てただけの、立派に「校外」であった。学校の周囲は凡て桑樹園であった。9/―この月、同志社英学校に余科(神学部)を併置。「熊本バンド」の中でも、熊本洋学校を卒業して来た学生たちは、学力の程度も高かった。同志社は彼らのために、急遽、「余科」を設置したという。同志社は急速に発展していく。―この年、志士顕彰団体「京都養正社」が創立される。内閣顧問木戸孝允と京都府権知事槙村正直が中心となり作った組織で、祭られる対象は「戊午(安政5年・1858)以来、其の身多年王事に憂労して終に非命に死」んだ者たちとなる。10/―この月、徳富猪一郎(蘇峰)(1863~1957)、東京から横浜に行き、1、2泊ののち、横浜港から神戸に向けて出航する。京都の同志社英学校入学のためである。10/14この日から二日にわたり、京都霊山において招魂祭が、養正社による私祭として行われる。10/20 徳富猪一郎(蘇峰)(1863~1957)、同志社英学校入学。10/24「女子塾京都ホーム開設」。米国人女性宣教師A・J・スタークウェザーが、J・D・デイヴィス宅(京都御苑内の柳原前光邸)で、女子塾を正式に開始する。同志社女子大学の起源。現在の京都迎賓館の地。寄宿学校であったことから、「Kioto Home(京都ホーム)」とも呼ばれた。開学当初の生徒数は、山本みね(峰)(1862~1887)、横井みや(宮)(1862~1952)ら寄宿生4人・通学生8名の12人。新島八重(1845~1932)も教鞭を執った。こうして、京都における最初のキリスト教主義の女子教育が始まる。これは翌年、「同志社分校女紅場」として認可され、すぐに「同志社女学校」と改称される。西暦1876三十番教室(同志社大学提供)第二寮(同志社大学提供)京都ホーム時代から学んでいた生徒たち 前列左から高松仙、本間春、横井宮、後列左から大西静、山本峯(同志社社史資料センター提供)