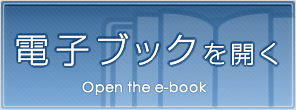戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 10/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 8 ? ?角すみ屋やもてなしの 文化美術館 (期間公開) 六条柳町(六条三筋町)遊廓が、寛永17年(1640)、朱雀野(島原)に移転、翌年開設し、「新屋敷」という地名ができる。六条三筋町は、南北は五条から六条....
? 8 ? ?角すみ屋やもてなしの 文化美術館 (期間公開) 六条柳町(六条三筋町)遊廓が、寛永17年(1640)、朱雀野(島原)に移転、翌年開設し、「新屋敷」という地名ができる。六条三筋町は、南北は五条から六条通、東西は室町から新町通の一画、ここから狭い道を通って、傾城たちがぞろぞろと西へ西へと大移動する様は、「あたかも島原の乱の如し」と流布したことにより、「島原」と呼ばれるようになるという。慶応3年(1867)1月1日~3日まで、新選組伊東甲子太郎、斎藤一、永倉新八ら、が居続ける。同年11月15日の龍馬暗殺日には、新選組近藤勇は、会津藩公用人山本覚馬と、角屋で過ごすという。明治期になると、歌舞音曲を供して遊宴する街、「花街」として発展する。島原には「揚屋」と「置屋」という業種があり、「揚屋」は遊宴の場として大座敷と大厨房を備え、料亭の機能を果たす。「置屋」は太夫や芸妓を抱えて教育し、揚屋へ派遣する業種。「輪違屋」は置屋。これは「送り込み制」と呼ばれ、祇園などの花街に残るシステムだ。角屋は、島原開設当初から建物・家督を維持しつづけ、江戸期の饗宴・もてなしの文化の場である揚屋建築の唯一の遺構として、昭和27年(1952)に国の重要文化財に指定された。?輪わ違ちがい屋や (現在も営業中)揚あげ屋やである角屋と並び古い由緒をもつ島原の置おき屋やで、元禄年間(1688-1704)創建と伝える。現在の建物は安政4年(1857)の再建で、明治4年(1871)にはほぼ現在の姿になった。輪違屋の遊女は新選組隊士と関わりが深く、山南敬助と明あけ里さと、平間重助と糸いと里さと、伊東甲子太郎と花はな香か太た夫ゆうが馴染みの仲だったという。現在でも揚屋と置屋を兼ね備えた現役の店であり、日本で 唯一「太夫」が居る所とされる。2階の客室の内、傘を貼った襖をたてる「傘の間」と、土壁に赤や黒の押型の紅葉を散らす「紅葉の間」が名高い。2階との間の階段が全部で5つあり、客同士の鉢合わせを避けるためだそうだ。侶3000人により移し、飛雲閣前庭を作庭する。寛永10年(1633)、対面所(家康伏見城、現・書院)を移し建造、虎渓の庭が作庭されたとみられている。聚楽第遺構と伝える飛雲閣は、金閣、銀閣と共に「京の三名閣」の一つに数えられる。境内地東南に位置する「滴翠園」の中に建てられ柿葺の三層からなる楼閣建築で、前面が滄浪池に面し、舟で出入りするようにつくられている。伏見城遺構と伝える唐門は、建築細部の彫刻を眺めていると日の暮れるのも忘れるといわれ、「日暮らし門」と呼ばれる。?島原大おお門もん寛永7年(1630)、六条柳町遊廓の移転が決定する。実際の移転は寛永17年(1640)で、朱す雀ざく野の(島原)に移転する。日本初の幕府公認の公許遊廊島原の正門で、当時四周は堀と塀で囲まれ門はその東辺北寄りに設けられていた。一間幅、本瓦葺、切妻の高麗門。門内は通りの左右に格子造りの古い揚屋、置屋が整然と並んでいたという。門前に通称「出口の柳」「さらば垣」、門前の道筋には、「思案橋」と粋に名づけられた橋もあった。角屋もてなしの文化美術館島原大門輪違屋