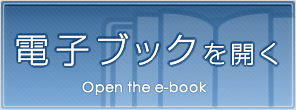戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 2/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
目次P3 京都全体索引図P32 索引一覧P33 鉄道路線図・奥付■コース概略???????????P4~6コース 1JR京都駅より豊国神社、豊国廟コースJR京都駅の正面口を出る。京都タワーを見上げながら烏丸通を東本願寺へ。11月....
目次P3 京都全体索引図P32 索引一覧P33 鉄道路線図・奥付■コース概略???????????P4~6コース 1JR京都駅より豊国神社、豊国廟コースJR京都駅の正面口を出る。京都タワーを見上げながら烏丸通を東本願寺へ。11月下旬は、寺前の大イチョウと桜の紅葉が迎えてくれる。その頃(11/21~28)本願寺の一大行事、報恩講が行われる。正面門前通を東へ歩むと、渉成園(枳殻亭)と呼ばれる「隠れた名園」で石川丈山作庭。石山合戦に乗じた家康により、東本願寺は西本願寺の参道の東に創設された。一大宗教へと発展し続ける本願寺を二つに分けるため、教如の徹底抗戦と顕如の休戦という意見対立を利用したのだ。なお、今も正面通りとして名前が残る道は旧道。渉成園を出て「ひと・まち交流館 京都」へ寄ったら、正面通りを東へ高瀬川の正面橋を渡る。幕末この辺りの七条新地「鳥岩楼」で龍馬はお龍と運命的出会いをしたところである。高瀬川の第一期工事も正面まであった。鴨川の正面橋を東へ渡り、東へ歩むと右側本町街道筋の角に古い料亭が残っている。石田三成の軍師「島左近邸跡」である。この辺りは、化石のような商店街で古い「かしわ屋さん」があったり、銭湯があったり面白い散策の道である。東へ歩むと小さい寺・烏寺の熊谷山専定寺(浄土宗)。専定坊がこの地に休んでいると二羽のカラスが「今日は熊谷蓮生坊(直実)の極楽往生の日」と語り熊野権現に化して飛び去ったという。烏寺の所以だ。この向かいの耳塚は大仏鋳造の鋳型を土中に埋めた御影塚とも、秀吉朝鮮出兵の際、敵兵の耳を切って日本に送らせた塚ともいう。韓国の方のお参りが多く常に花が一杯である。東へ歩む豊国神社。本殿正面の唐門(国宝)は、旧伏見城の遺構という。秀吉ゆかりのものがいっぱいある。その北側に大坂冬の陣のきっかけとなった「国家安康」銘の鐘を見学して、ここに巨大な大仏様がおわした大仏殿があったことを思う。ここの南側のレトロな博物館へと歩む。巨大石垣が残る姿は異様である。三十三間堂が見える。大仏殿遺構の南門「南大門」と築地塀「太閤塀」を見よう、桃山の豪壮さそのものである。坂本龍馬はこの南側にお龍と住んでいたという。近くに養源院。淀殿が、父浅井長政の追善供養として建立、伏見城の血天井があるので有名。東へ登っていく京都女子大の通学路(女坂)だ。新日吉神宮を越え、更に登る石段に挑戦、頂上に秀吉の墓がある。参拝してもとの段を下ると、大坂落城の際、脱出し伏見に逃れた、秀頼の一子国松の墓と京極竜子の墓があり「あわれを誘う」。東山七条バス停まで歩くか隣の妙法院へ行ってみよう。幕末「七卿落ち」で有名な寺だが、室町期の佐々木道誉の「妙法院焼討」は余り知られていない。すぐ南側には、秀吉ゆかりの寺・智積院。長谷川等伯の国宝「障壁画」は特に有名。P7~8コース 2 JR京都駅より西を歩く 西本願寺・島原コース駅ビルに沿って西側を歩くと日本一長い駅舎が判る。これは明治期、秀吉が築いたお土居の上に建設されたからだ。アパホテルの横、油小路塩小路下ルに明王院不動堂がある。ここのお不動様は地中深く祀られていて「禁門の変」の大火でも難を逃れられたとか。この辺りに「新選組」の最後の不動堂村屯所があったのだが幻の屯所となっている。義経一行と宇治で別れた佐藤忠信の屋敷跡で、彼が追討の北条氏に攻められ討死したところである。この付近の油小路七条は新選組の一大事件、「油小路の変」とか、「天満屋事変騒動の跡」、「近藤勇の妾宅跡」、「西本願寺屯所跡」と新選組ゆかりの深い土地である。油小路から堀川へ出る角に、京町家の和菓子屋さんが目に付く。この老舗は西本願寺の名物菓子製造の松風屋さん(亀屋陸奥)だ。この松風は石山本願寺和睦で顕如上人が雑賀衆と雑賀への道筋で食糧方がお菓子を差上げ、これがお気に入りになられ、西本願寺の銘菓となったもの。和紙にカステイラの判焼きのような板状の菓子を巻いたものが原型で、店には少し並んでいる。お西さん(西本願寺)本堂は御影堂「みえいどう」、これに対してお東さん(東本願寺)は「ごえいどう」と呼ぶ。西本願寺には、国宝の建造物旧伏見城の遺構が多くある。少し南へ歩いて龍谷大学明治学舎を見学して、その隣に国宝唐門を見る。また境内に戻ると大イチョウ「水吹きイチョウ」と呼ばれ聖木だ。「禁門の大火」の時、水を吹き上げ本願寺は類焼から守られたという。そこには新選組の西本願寺屯所の遺構、「太鼓楼」が残る。この北側には元本圀寺跡の大駐車場。鎌倉、室町期は日蓮宗全盛、本願寺も元は本国寺(本圀寺)の境内であった。元の正門前に大きな「南妙法蓮華経」の石碑が残る。加藤清正ゆかりの塔頭寺が多くある。ここから西へ5分程で、島原大門に着く、江戸期の日本一の遊里に風情が漂う。重文の「角屋」と市文化財「輪違屋」が江戸期の姿をとどめている。「新選組記念館」にもどうぞ。少し歩くとJR丹波口駅で「京の七口の一つ」丹波口だ。駅前の千本通りは平安京朱雀大路跡、構内に遺跡表示あり、近くに「平安京朱雀大路跡」碑もある。P9~10コース 3 信長コース 本能寺から阿弥陀寺四条烏丸(地下鉄烏丸線、阪急電車、市バス)をスタートして四条通北側を西へ歩く。油小路通を北へ少し歩むと本能寺跡の石碑、旧本能小学校の前に建っている。最近の発掘調査の結果、相当広いお寺で東側の「南蛮寺」と接していた。加藤廣著の歴史小説「信長の棺」では抜け穴道があったとされているが、あったかもしれない。蛸薬師通を、西洞院通を越えて東へ新町通を少し下ると東側に「茶屋四郎次郎邸跡(駒札)」がある。この辺りは、京町家の家並の美しい所である。蛸薬師通を東へ更に歩むと「南蛮寺跡碑」があり、ここから本能寺東側までと広大な寺であり何か本能寺との関連が頭に浮んでくる。本能寺の変の際、南蛮寺の望楼から外国人宣教師が事件を観察し戦国時代の京都史跡を歩く 13コース?はじめに?京都には「戦国」に関連する多くの史跡や社寺などが点在しています。京都は戦国時代の日本の中でその動乱の中心だったと言えます。本書籍は、戦国の京都を地図に再現し、読者の方々が迷うことなく、その遺跡等を巡っていただけるよう願い、企画いたしました。京都を13のコースに分けて実際に歩ける地図として紹介し、1エリアで数ヶ所の史跡などの紹介、より実用性の高いガイドブックに仕上げました。戦国ファンや歴史ファンはもちろんのこと、多くの京都ファンの多くの方々にも、ご利用いただけたらと願っております。「龍馬・新選組らの京都史跡を歩く13コース」、「平清盛・源平時代の京都史跡を歩く13コース」、「明治・大正時代の京都史跡を歩く13コース」と、お陰様でシリーズ4作目の刊行となりました。ありがとうございます。最後になりましたが、ご協力いただきました取材先様はじめスタッフの皆々様に、厚く御礼申し上げます。歴史関連史跡神社寺石碑宿泊バス停紹介史跡史跡(痕跡なし)地図記号 コース紹介物件は赤字本書地図では、戦国時代の情報を主として、当時の物件敷地を以下色で現在の地図と重ね合わせて表記してあります。戦国時御所内敷地戦国時社寺の敷地現在の敷地