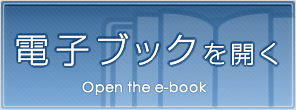戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 4/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 2 ? P20~21コース 8 阪急大山崎駅~天王山コース河原町駅から梅田行きの阪急京都本線に乗る。天王山の下に大山崎駅がある。大山崎町歴史資料館では、山崎合戦の様子をビデオで紹介、千利休が作った茶室「待庵」の....
? 2 ? P20~21コース 8 阪急大山崎駅~天王山コース河原町駅から梅田行きの阪急京都本線に乗る。天王山の下に大山崎駅がある。大山崎町歴史資料館では、山崎合戦の様子をビデオで紹介、千利休が作った茶室「待庵」の実物大模型が展示してある。駅前の妙喜庵の国宝茶室「待庵」(拝観予約制)は、千利休と秀吉のゆかりの名茶室。西国街道沿いに油祖 離宮八満宮、戦国期には油座があり、斎藤道三(マムシと恐れられていた武将)はここで少年期は働いていた。淀川の河川の要港で山崎津(やまさきのつ)(京都府乙訓郡大山崎町大山崎)といわれて繁栄しており、芸能者などの集まる散所(さんじよ)の一つといわれた。また、東大寺の領地であり、東大寺という地名も大阪府側に残る。「禁門の変」の際は一大戦場となる。戦国期は秀吉対光秀の天下分け目の天王山の戦いの舞台。宝積寺へ登る(通称・宝寺)、さらに少し登ると「旗立松」、良い展望の高台だ。そこから登ると幕末「禁門の変」の十七烈士の墓が並ぶ。この土地の人々は昔「禁門の変」の義士の墓を「残念さん」と呼び拝していたという。頂上城跡(山崎城跡)を登ってみよう。P22~23コース 9 花園~仁和寺コースJR花園駅に降り立つと、向かいに法金剛院、ここは白河天皇の娘、崇徳上皇の母、待賢門院のお寺。平安京唯一の庭が残る。西行も彼女を慕って来寺したという。彼は北面の武士で待賢門院の美しさに魅かれ、身分違いの失恋の苦しさから仏門に入ったと言われており、その一子・崇徳上皇の流刑地の墓所、白峯(香川県坂出市)で上皇の魂を鎮魂したとの話「雨月物語」は有名である。そのあと妙心寺へ5分程歩き、寺門を入って右側に明智風呂と云う当時の沐浴室(現在は蒸し風呂)が文化財として残る。明智の叔父が建てたと言われその名がついている。塔頭寺院が整然と並んでいる。戦国ゆかりの寺が多く、真田幸村の墓など他多くある。西門を出ると御室仁和寺は近い。ここは京の桜の名所、御室のおかめ桜として「花は低いが美しい八重の花と咲き」。毎年4月20日頃に満開となる。すぐ近くに兼好法師が庵を結んだ「双ケ丘(ならびがおか)」がある。この山頂に登って仁和寺を遠望するのも良い。仁和寺の保護で名作を作窯した、野々村仁清窯遺跡がある。P24~25コース 10 金戒光明寺~銀閣寺市バス岡崎神社前で降りる。北側岡崎神社の横の道を北へ入って行く、うす暗い木立の道を進むと金戒光明寺の南通用口の石段と寺門に出会う。墓地の入口に出る。左へ行けば山門や本堂、この前に熊谷直実の「鎧掛けの松」がある。須磨の源平合戦で、息子の様な貴公子の命を奪った彼は、武士を捨て、法然に救いを求めた遺跡である。金戒光明寺は、幕末には悲劇の会津侯、松平容保が入った寺で、一時京都守護職本陣となった所。墓地の左側に巨大な供養塔がある、春日局が建立した、徳川秀忠夫人の供養墓だ。墓地中ほどで左へ入る。信州上田藩士赤松小三郎の墓ありの指標が立ち、彼は西洋兵学者で、弟子の薩摩の中村半次郎らに東洞院通で暗殺された。近年、石碑を新調している。うす暗い木立の下に無縁墓が左に並ぶ道を登ると西雲院の門前に着く。中に入り会津小鉄の大きい墓、守護職の荷役をして戊辰の役(鳥羽・伏見)の会津武士の死体を、この会津墓地へ運び埋葬した義士である。法然が、ここから西に「紫の雲」をご覧になって悟られたという伝承の石(紫雲石)がある。会津墓地はこの寺が管理している。西雲院からすぐに一段高く囲まれた大きい墓地「会津墓地」入ったら左に大きい石碑と桜がある。容保公の孫の勢津子姫が昭和3年(1928)に昭和天皇の弟君と結婚され、会津は逆賊の汚名が外された。桜はその年、参拝に来寺された記念の桜だ。京都会津会によりこの墓地は美しく保たれている。少し北へ歩くと背中合わせに真如堂(紅葉の名所)に着く。何かこの二寺は軍事的意味があると思わざるを得ない。東側を下って「哲学の道」に入る。法然院とか、お寺が多くある。人が多くなってきたら銀閣寺道、やおら土産物屋をのぞいていたら銀閣寺門前に着いた。西へ戻ると銀閣寺前そして銀閣寺道バス停だP26~27コース 11 地下鉄東山駅から知恩院・南禅寺へ地下鉄東西線東山駅を出ると、美しい川「白川」が流れている。東岸を少し歩くと、明智光秀首塚碑が町家の中に建っている。比叡山を水源に流れ出している清流が気持ち良い散策路で、小さい和菓子屋がある。「京のおまん」は美味しい、一、二個求めて食べるのも良い。知恩院古門から知恩院へ、古門の前は古門前と呼ばれ古美術商街である。知恩院の巨大な三門へ、石段を登る。この寺も徳川氏が建てた、まるで城の様な大寺である。徳川氏関係の墓が多くある。本堂(御影堂)の屋根裏の「甚五郎の忘れ傘」を見て北へ歩く。平成31年までは、平成の大修理で、現場見学会等でしか見られない予定。石段を下りると、北隣は青蓮院門跡。「熾盛光如来曼荼羅」(しじょうこうにょらいまんだら)を本尊として、国宝「青不動明王」を有する「門跡寺院」(天台宗三門跡)で、今も東久邇宮家が門跡されている格の高いお寺だ。親鸞はここで得度され比叡山に登られた。三条通に出る手前を右へ入ると粟田神社に入る。参拝して三条通へ、この向かい小路を入ると相槌稲荷神社がある、この辺りでは昔、日本刀を作っていた。砂鉄は山科に良度の玉鋼が出た。今も「たたら遺跡」があり、天皇家の名刀はここで生まれたという、殆んど今は知られていないスポットである。さらに三条通北側を西進、ウェスティン都ホテルを右に見て琵琶湖疏水記念館やインクライン遺跡を見よう。琵琶湖疏水は隣の南禅寺を抜けて北へと流れていく。境内には水路閣というレトロなものや、有名歴史人たちの墓も多い塔頭寺院がある。付近は湯豆腐が名物である。地下鉄へと続く近道にあるトンネルは、ねじりまんぽ(陽気発処)という見所である。P28~29コース 12 京阪清水五条~祇園石段下コース京阪地下鉄、清水五条駅を上ると、目の前に五条大橋、この北側を西へ渡ると木屋町通、「高瀬川」が流れる。この西側に旧道が残る、レトロなコーヒー店の下の石段を下りると、川に沿って古道が残る。昔は高瀬舟をロープで両岸から人夫が引き、二条まで、客や荷を運んでいた。桜が散る「花筏」の頃に歩くと最高の風景に出合う。万寿寺橋までこの道は残っている。鴨川を東へ松原橋を渡る。これが本当の「五条大橋」で牛若丸と弁慶の決闘地である。宮川町筋に入る。風情の残る石畳とお茶屋の提灯。宮川町歌舞練場の横道を東へ出ると「ゑびすさん」と建仁寺の西門へ。建仁寺、安国寺恵瓊の首塚とか、建仁寺塔頭寺院は我国武将ゆかりの寺が多くある。黒田官兵衛子・長政の念持仏は両足院毘沙門天堂にあり、黒田長政が関ヶ原の際に兜に納めて出陣した秘仏・毘沙門天像だ。南門を出ると八坂の塔の道。東へ上って東山通を更に上ると庚申堂そして八坂の搭(法観寺)に着く。下って高台寺下から石塀小路の迷路を下河原通に出る、色気いっぱいの気配漂うゾーンである。安井の金毘羅さんに参って、京都井伊美術館も近い。祇園歌舞練場の東の道を北へ入ると崇徳さんと呼ばれる怪奇スポットに会う(崇徳御廟)。北へ向かい西進すれば、花見小路通。赤壁の「一力」を西へ、京阪祗園四条駅はすぐである。P30~31コース 13 東山七条~伏見稲荷コース泉涌寺通を登ると左に「即成院」、那須与一の墓の石柱、この手前に、林の中に暗い墓地。ここは、高台寺党・伊東甲子太郎らのお墓、戒光寺の飛び地である。少し離れて戒光寺がある。伊東らの墓には戒光寺さんの許可を得てお参りしなければならない。泉涌寺は「御寺」と呼ばれる皇室ゆかりのお寺。「楊貴妃観音さん(観音菩薩坐像)は別嬪さんですえ。別嬪さんになりたい人はお参りをしておくれやすえ!」。ここから東福寺までウォーキング。京都市内最高の紅葉の名刹だが、臥雲橋から見られて入場料も不要。その通天橋の景色は最高の別嬪さんですえ!!金堂や国宝三門は巨大、その西側の「東司」は重要文化財の便所(室町時代の禅宗式便所)である。自由に覘けるぞ!南門を出ると、朝日姫(家康の妻で秀吉の妹)の墓のある塔頭南明院、権力者(秀吉)の陰の女の悲劇。ここを南へ歩くと「お稲荷さん」の本拠「伏見稲荷」。雀の串焼きの匂いがしてくる。