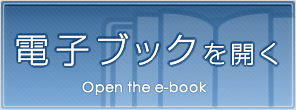戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 7/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 5 ??豊とよ国くに神社明治元年(1868)、明治天皇の意向により、新政府は新いま日ひ吉え神宮の神楽殿を仮社殿として再興を布告、豊臣秀吉を祀る。明治13....
? 5 ??豊とよ国くに神社明治元年(1868)、明治天皇の意向により、新政府は新いま日ひ吉え神宮の神楽殿を仮社殿として再興を布告、豊臣秀吉を祀る。明治13年(1880)9月15日、社殿は竣工。1881年、豊国神社が、社地を現在地(方広寺大仏殿跡地)に移して創建された。宝物も返却されている。寛永4年(1627)、江戸幕府は、二条城唐門を南禅寺に下す。そして、塔頭金こん地ち院いんから移築、豊国神社の唐門となる。伏見城の遺構という。宝物館に秀吉遺品を納めた「唐櫃」・「黄紗綾地菊桐紋付胴服」(秀吉の羽織)などがある。?方広寺文禄4年(1595)、方広寺大仏殿竣工。境内は東西約55m、南北約90mの広大な敷地を有し、現在の豊国神社と京都国立博物館の地、蓮華王院(三十三間堂)も取り込んでいた。大仏殿も、高さ50m、前面82mの巨大な建造物だった。慶長19年(1614)、豊