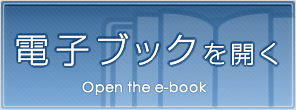戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 8/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている8ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 6 ? 臣秀ひで頼よりにより、大仏殿と大仏、梵鐘が復興される。だが、「鐘銘事件」により、家康は開眼供養を延期させる。そして、大仏殿は破却される。「鐘銘事件」の発端となったこの鐘は、家康によって潰されるこ....
? 6 ? 臣秀ひで頼よりにより、大仏殿と大仏、梵鐘が復興される。だが、「鐘銘事件」により、家康は開眼供養を延期させる。そして、大仏殿は破却される。「鐘銘事件」の発端となったこの鐘は、家康によって潰されることはなく、豊臣家没後、現在の京都国立博物館付近に雨ざらしとなっていたという。近代になり、現在地に移された。?大仏殿石垣碑方広寺大仏造営にあたり秀吉は諸大名に命じ、各地から巨石を集めさせた。諸大名はその大きさを争ったと伝え、巨石の表面にはそれぞれの家紋が刻まれていたという。俗に「石狩り」と云われた。延長約300mが現存する。蒲がも生う氏うじ郷さとの石(約3.6m×約7.2m)や前田加賀守泣き石(石垣最北端)が名高い。今でも石に白い筋「涙の痕」がある11養源院養源院の寺名は浅井長政の院号から採られた。文禄3年(1594)5月に秀吉の側室・淀殿が、父・浅井長政の21回忌供養のために、秀吉に願って成伯法印(長政の従弟で比叡山の僧)を開山として創建された。その後、元和5年に焼失するが、元和7年(1621)、徳川秀忠の正室・崇源院(お江ごう)の願いにより再建された。以後、徳川家の菩提所となる。本堂は元和5年に破却された秀吉の伏見城の遺材「中の御殿」をもって元和9年頃、本堂を建てる。その頃、俵屋宗達が、杉戸絵などを描く。本堂の正面と左右の廊下の天井は血天井として知られる。1213三十三間堂南大門・太閤塀三十三間堂の東南にある壮大な八脚門が南大門。秀吉の大仏殿は焼失したが、方広寺の西門と南門、それに続く築地塀の一部は現在に遺った。西門は現在、東寺の南大門として移されている。三十三間堂南大門は慶長5年(1600)の建立とされる。「太閤塀」と呼ぶ築地塀は、天正16年(1588)建立とされ、秀吉が寄進した塀である。14新いま日ひ吉え神宮江戸時代は、豊臣秀吉に関するものは全て壊され禁止となる。しかし太閤さんの人気は高く、隠れて崇拝する人もいた。密かに太閤さんを信仰する人々が集ったのが新日吉神宮だった。境内にある「樹下社(このもとのやしろ)」は「豊ほう国こく神じん社じゃ」とも呼ばれ、この樹下社に、秀吉信仰をする人々が訪れたという。金灯篭は、かつて豊国神社の本殿の軒下に釣り下げられていたもので、片桐且かつ元もと・貞隆の寄進。15豊ほう国こく廟びょう慶長4年(1599)から造成された豊国廟の豊臣秀吉墓は、その後徳川氏により破却された。創建当初には、その裾にはかつて黒田官兵衛・石田三成らの僧坊が並んでいたという。明治30年(1897)、秀吉の300年忌に際し廟宇が建設され、翌年再建、黒田・蜂須賀等の旧家臣等により、墳上には巨大な五輪石塔が建てられた。廟墓は、大徳寺総見院にある信長の墓が雛形にされたという。設計は、伊東忠太。16太たい閤こう坦だいら(豊国神社跡)(国松(秀頼の子)墓、京極竜子(秀吉側室松の丸殿)墓)新京極誓願寺から徒歩2分ほど、寺町通六角上ルに、かつて松の丸殿と国松の墓があったとされる。明治新政府の繁華街政策で誓願寺の土地が没収され、この二人の墓が取り残された。明治37年(1904)、人々は哀れに思い、秀吉の眠る豊国廟に墓を移したという。17智ち積しゃく院いん豊臣家滅亡後の元和元年(1615)、徳川家康は帰き依えしていた智積院住職へ土地を寄進した。その土地とは、秀吉が夭折した長男の鶴松(棄丸)の菩提を弔うために建立した祥雲寺だった。智積院は祥雲寺の建物や寺宝、豊国社(現・豊国神社)の堂宇や梵鐘など全てを引き継ぐ形でこの地に中興した。