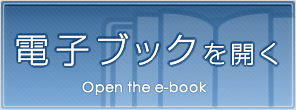戦国時代の京都の史跡を歩く13コース page 9/12
このページは 戦国時代の京都の史跡を歩く13コース の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
? 7 ?4km2コース約2 時間30 分JR京都駅(京都駅は日本一長い駅である。ビルに沿って西へ歩くと良く分かる)?(560m)??明王院不動堂(新選組屯所所在地)?(油小路を北へ255m)??本光寺(伊東甲子太郎絶命の地碑)?....
? 7 ?4km2コース約2 時間30 分JR京都駅(京都駅は日本一長い駅である。ビルに沿って西へ歩くと良く分かる)?(560m)??明王院不動堂(新選組屯所所在地)?(油小路を北へ255m)??本光寺(伊東甲子太郎絶命の地碑)?(120m)?油小路七条(油小路決闘地)?(80m)?七条堀川(?「亀屋陸奥」和菓子商)?(390m)??西本願寺(本堂へは唐門から570m)?(565m)??本圀寺の題目石碑(南無妙法蓮華経の大石碑)?(500m)??島原大門?(195m)??角屋もてなしの文化美術館?(190m)??輪違屋?(330m)??新選組記念館?(250m)?JR丹波口駅(朱雀大路地碑)JR 京都駅より西を歩く西本願寺・島原コース?西本願寺天正19年(1591)、秀吉は六条堀川に土地を与え、寺は大坂より移転。翌年、顕けん如にょ没後、教きょう如にょは秀吉により寄進された七条堀川(現在の西本願寺の地)の本願寺門跡となる。その後、秀吉により教如は門主の座を奪われ、三男・准じゅん如にょが門主となることが認可される。のち、徳川家康により、本願寺(東本願寺)が建立され、本願寺は東西に分裂。御影堂と阿弥陀堂はともに重要文化財。書院の庭園(特別名勝)は桃山文化を代表する枯山水様式。その他、わが国最古の能舞台となる北能舞台、唐門など桃山文化を今に伝える国宝建造物を多数擁している。江戸時代の慶長15年(1610)、聚楽第庭石を門徒・僧