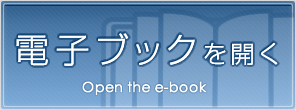武田家三代年表帖(上巻) page 4/20
このページは 武田家三代年表帖(上巻) の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
4の甲相駿三国同盟への伏線となる。この年、四郎(後の武田勝頼)が誕生した。今川・北条との関係が安定したことで晴信(信玄)は、同年5月3日佐久郡侵攻を本格化させ、天文16年(1547)6月1日には、その家法「甲州....
4の甲相駿三国同盟への伏線となる。この年、四郎(後の武田勝頼)が誕生した。今川・北条との関係が安定したことで晴信(信玄)は、同年5月3日佐久郡侵攻を本格化させ、天文16年(1547)6月1日には、その家法「甲州法度之次第」26ヶ条を定め、甲斐・信濃に公布するまでとなる。天文16年(1547)閏7月24日、関東管領勢に支援され、佐久で唯一抵抗する志賀城の笠原清繁を攻め、同年8月6日の小田井原の戦いで武田軍は関東管領上杉・笠原連合軍に大勝、8月11日佐久郡の平定を完了する。天文17年(1548)1月8日、信濃国北部に勢力を誇る葛尾城主・村上義清が佐久郡へ出陣。佐久郡は村上義清の勢力圏内でもあり、ここに武田・村上両者は遂に直接衝突するに及ぶこととなる。2月14日晴信(信玄)は、村上義清と上田原で激突する(上田原の戦い)。この合戦で信玄は、武田家の当主となって初めて敗戦の苦渋を味わう。自分の右腕ともいうべき諏訪郡代の板垣信方、甘利虎泰、才間河内守、初鹿野伝右衛門高利らをはじめ多くの将兵を失った。この機に乗じて同年4月5日、小笠原長時が村上義清軍らと共に諏訪に侵攻して来るが、晴信(信玄)は、7月19日の塩尻峠の戦いで小笠原軍を急襲し大勝した。天文18年(1549)7月以降、晴信(信玄)は、伊那・佐久の拠点強化等をする。天文19年(1550年)7月、晴信は小笠原領に侵攻する。これに対して小笠原長時にはすでに抵抗する力は無く、林城を放棄して村上義清のもとへ逃走した。こうして、信濃中南部の大半は武田の制圧下になった。同月23日には、信濃経略の基地として深志城(のちの松本城)の修築を始める勢いに乗った晴信は同年9月9日、村上義清の支城である戸石城を攻める。そんな折の9月13日、村上義清は、高梨政頼と、晴信(信玄)の信濃侵攻に備え、宿年の対立を和解して連合した。戦況不利を判断して、30日武田軍議で、戸石城から退却を決定する。しかし、10月1日の退却戦で武田軍は、後世に戸石崩れと伝えられる大敗を喫した。天文20年(1551)2月12日、晴信(信玄)は除髪する。同年5月26日、武田の将・真田幸隆(幸綱)(信繁の祖父)(1513~1574)、計策をめぐらし村上方城主山田国政武田勝頼